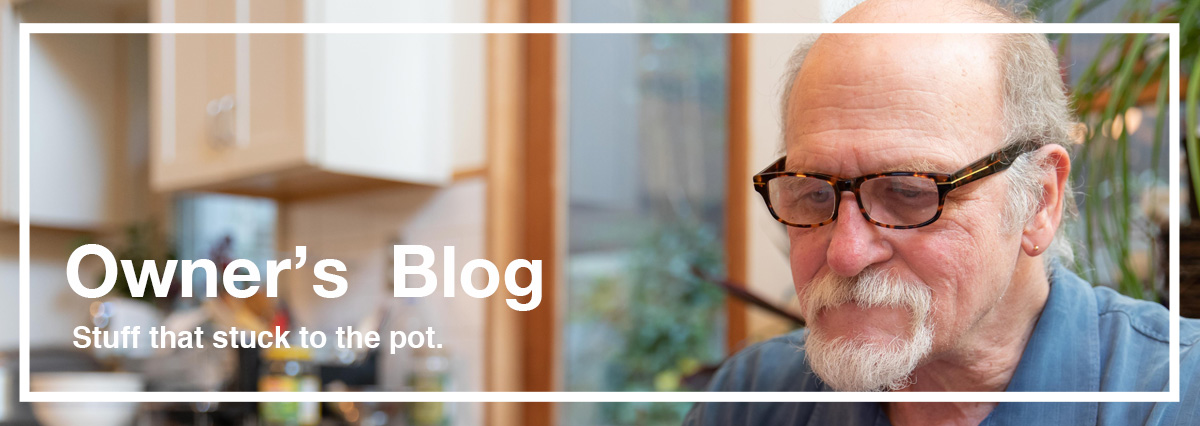
ニューヨークで育つということがいかに“特別”なことであったのか、世界中の様々な都市に住んできた経験がある今だからこそ実感することができる。
子供の頃住んでいたブロンクスのアパートから徒歩5封圏内には、イタリアンレストランやユダヤ料理店、そして「こんなパン屋が近所にあったら最高だなあ」と思えるようなドイツ系の家族が営むベーカリーもあった。地下鉄で少しいけば、大抵どんな国の料理でも食べることができた。しかも本場の味を!
近所のモンテ・ドーロというイタリアンレストランを経営するアンジェロは、まるで濃厚なマリナラソースを彷彿させるような強い訛りで話す男だった。 シュテンツラーさんはホロコーストを生き抜いた人で、ユダヤ系デリカッセンを営んでいた。英語とイディッシュ語を混ぜたような言葉で彼はよくロールキャベツを私たちに勧めては 「これを食べなければ、君は空腹のあまり餓死してしまうし、私も商売が出来ず飢え死んでしまうよ」なんて冗談を言った。多種多様な人々や食べ物の香りに囲まれる生活は楽しいものだった。
 私の国際色豊かな食の世界、その中心には祖母のイタリア料理が並んだテーブルがあった。それを叔父、叔母、いとこ、孫やひ孫が囲んだ。 クリスマスやイースターのような大事な祝日ともなれば約30人(もしくはそれ以上)の人々が集まり盛大に祝った。そして祝い事に食はつきものだった。
私の国際色豊かな食の世界、その中心には祖母のイタリア料理が並んだテーブルがあった。それを叔父、叔母、いとこ、孫やひ孫が囲んだ。 クリスマスやイースターのような大事な祝日ともなれば約30人(もしくはそれ以上)の人々が集まり盛大に祝った。そして祝い事に食はつきものだった。
盛大なごちそうの一大準備はテス叔母さん、そして彼女の妹のベラ(私の母)が取り仕切った。買い出しにはアーサー通りにあるブロンクスのリトル・イタリーへ行かなければ始まらない。
 買い物はあえてイタリア語で行われた。 姉妹が同郷と分かれば、大げさなジェスチャーやにぎやかな笑い声、「これ、ちょっと高いんじゃないの?」という冗談も許された。 “bella lingua(美しき言語)”を使うことで店主との距離も縮まり、家族同士の意外な繋がりを発見することもよくあった。親戚がイタリアの同じ地域出身だったり、いとこと肉屋の甥っ子が同じ学校に通っていたり… どんなに小さな共通点でも、ボローニャソーセージの割引や、小さなウィンクとおまけのカンノーリに十分な理由だった。
買い物はあえてイタリア語で行われた。 姉妹が同郷と分かれば、大げさなジェスチャーやにぎやかな笑い声、「これ、ちょっと高いんじゃないの?」という冗談も許された。 “bella lingua(美しき言語)”を使うことで店主との距離も縮まり、家族同士の意外な繋がりを発見することもよくあった。親戚がイタリアの同じ地域出身だったり、いとこと肉屋の甥っ子が同じ学校に通っていたり… どんなに小さな共通点でも、ボローニャソーセージの割引や、小さなウィンクとおまけのカンノーリに十分な理由だった。
お祝いの当日は、早朝から祖母のキッチンに集まった。そこには、既にストーブの上で煮立っている巨大なコーヒーのポットや、アーサー通りでの収穫の品々が大きな木製のテーブルの上に広げられていた。
メニューやレシピの全てはテス叔母さんの頭の中にあった。叔母さんの動きに遅れずについていくか、邪魔にならないようにするか、私たちにはその二択しかなかったのだ。
子供たちの担当は決まって木製のクランクハンドルがついたおろし器で山のようなパルメザンチーズをすりおろすことだった。(ちなみに私の人生で初めての水ぶくれはこの仕事によるものだった)
手にべとべととくっつくゼッポレ(はちみつで浸した揚げパン)の型作り、そして包丁を扱えるくらいの年齢になったら、シート状の自家製パスタをフェットチーネの形に切るという仕事も任されるようになる。
 姉妹は料理に関するすべてを祖母から教わった。その祖母は、祖父アントニー(カゼルタ出身の農家の息子)のために料理を作った。働き者のアントニーは故郷の味を大切にした。堅焼きのずっしりとしたパン、ゆっくりと丁寧に煮込まれた濃厚なソース、自家製の芳醇なワイン…
姉妹は料理に関するすべてを祖母から教わった。その祖母は、祖父アントニー(カゼルタ出身の農家の息子)のために料理を作った。働き者のアントニーは故郷の味を大切にした。堅焼きのずっしりとしたパン、ゆっくりと丁寧に煮込まれた濃厚なソース、自家製の芳醇なワイン…
そのすべてが彼にとっては古き良き友の訪れのようなものだった。
キッチンでテスおばさんと母と時間を過ごす中でいくつか学んだことがある。
・美味しいパスタソースを作るには3種類の肉を3時間かけて調理する必要があるということ。
・料理とは、人に自慢するために作るものではなく、人を心地よくさせるために作るということ。
・共にテーブルを囲む人々がいてこそ、料理はより美味しくなるということ。
コメント